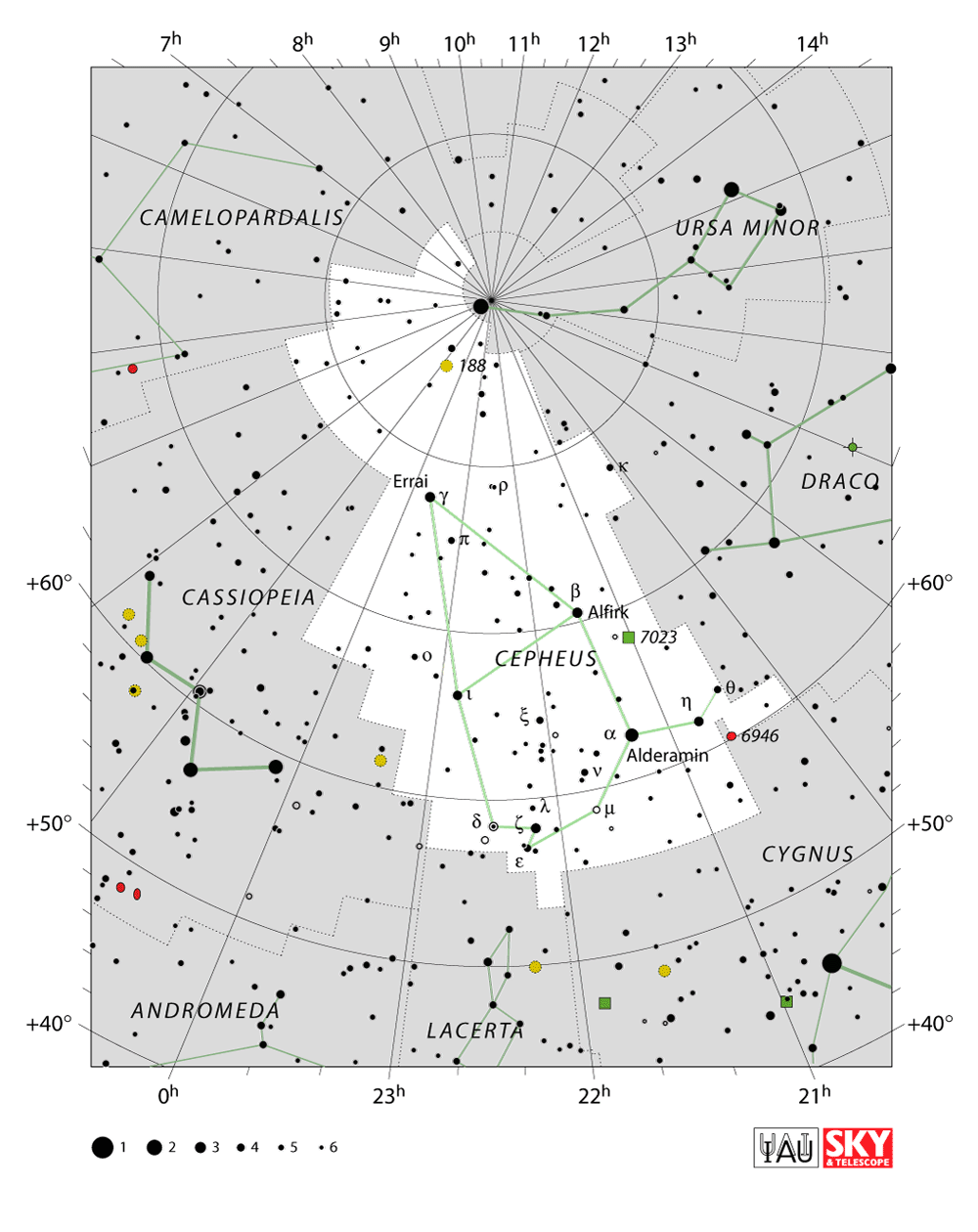ケフェウス座を語る。
ケフェウス座は秋の星座である。
暗い星ばかりであるが、特徴的な五角形であるため分かりやすい。
ケフェウスとは、ギリシア神話に登場するエチオピア王の名である。
王妃はカシオペア、その娘がアンドロメダである。
ケフェウスが実在の人物をモデルにしているのかどうかは、はっきりしていない。
ケフェウス座はトレミー48星座のうちの1つでもある。
トレミー48星座は、2世紀以来使われてきた。
しかし、18世紀に、トレミー48星座の中のアルゴ座がラカイユによって分割された。
ケフェウス座を含む残りの47星座は、すべて現在の88星座に引き継がれている。
ケフェウス座の主な恒星
ケフェウス座α [α Cep]
ケフェウス座αはケフェウス座で最も明るい恒星である。
アルデラミンという固有名で呼ばれる場合もある。
主系列星の段階を終え、赤色巨星に移行しつつあるA型星である。
ケフェウス座γ [γ Cep ]
ケフェウス座γはケフェウス座で2番目に明るい恒星である。
アルライという固有名で呼ばれる場合もある。
太陽系から45光年の距離にある。
K型星と赤色矮星の二重星である。
ケフェウス座β [β Cep ]
ケフェウス座βはケフェウス座で3番目に明るい恒星である。
アルフィルクという固有名で呼ばれる場合もある。
ケフェウス座β型変光星の代表例で、3.15等から3.21等の範囲で変光する。
太陽系から595光年の距離にある。
ケフェウス座δ[δ Cep]
ケフェウス型変光星(セファイド変光星)の代表例である。
ケフェウス座の主な星雲・星団
ケフェウス座にはメシエ天体がない。
NGC40

ケフェウス座の惑星状星雲NGC40
出展:NOAO:NGC 40
NGC40は膨張を続けており、3万年後には四散して消滅する。
NGC188
NGC188は散開星団である。 天の北極の近くにある。
ケフェウス座の散開星団NGC188
出展:Digital Sky Survey image of NGC 188
散開星団としては古い部類に入る。
NGC6946
NGC6946は銀河系外星雲である。

ケフェウス座の銀河系外星雲NGC6946
出展:Facing NGC 6946
ケフェイス座とはくちょう座の境界付近にある。
1798年9月9日にウイリアムハーシェルによって発見された。
20世紀以降に9個の超新星が出現している。
銀河系から1000万光年の距離だ。
NGC7129

ケフェウス座の散光星雲NGC7129
出展:Young Suns of NGC 7129
誕生後、100万年に満たない若い星が130個発見されている。
太陽系から3300光年の距離にある。
NGC7538
NGC7538は散光星雲である。

ケフェウス座の散光星雲NGC7538
出展:NGC 7538
その形から、ケフェウス座のバブル星雲とも呼ばれている。
(いて座、カシオペヤ座にもバブル星雲があるので、混乱しないよう注意が必要だ。)
NGC7538のなかでは、太陽系の300倍のスケールの原始星が発見されている。
これは今まで発見された原始星の中で最大のサイズである。
太陽系から9100光年の距離にある。
象の鼻星雲/IC1396
散開星団を取り囲む散光星雲である。

ケフェウス座の象の鼻星雲/IC1396
出展:The Elephant's Trunk in IC 1396
像の鼻星雲とも呼ばれている。
太陽系から2400光年離れている。
ケフェウス座のその他の天体
ガーネット・スター[μ Cep]
ケフェウス座μはガーネット・スターとも呼ばれている。
極端に赤いので、ウィリアム・ハーシェルがガーネットと表現した。
後年、これが広まりガーネット・スターと呼ばれるようになった。
SRC型の脈動変光星である。
[..さらに詳しく見る..]
CTA 1
CTA 1は、超新星残骸である。
CTA 1の内部には、ガンマ線パルサーの第一号として2008年にガンマ線天文衛星フェルミによって発見された。
太陽系から4600光年の距離にある。
このパルサーは約1万年前に誕生し、現在は316.86ミリ秒の周期を持つ。
ガンマ線パルサーのビームは、電波パルサーのビームよりも広いを考えられている。
スポンサーリンク
参考文献・サイト
Constellations
Star Tales
Chandra X-ray Observatory
Revised New General Catalogue and Index Catalogue
BBC:Constellations
2008/05/18
2010/06/12